将門口ノ宮神社 [千葉県]
2015/12/12
千葉県佐倉市大佐倉にある将門口ノ宮神社(まさかどくちのみやじんじゃ)です。
大佐倉駅の南の山中に鎮座する神社であり、祭神に佐倉ゆかりの英雄である平将門公と佐倉惣五郎が祀られています。
比較的小さな神社ですが、江戸時代に寄進された石鳥居は佐倉市の指定文化財になっているそうです。
平将門についてはこちらの記事を参照:【平将門とは?】
由緒
境内の石碑によれば、平安時代の関東の英雄である平将門公を祀るために同族の千葉氏によって建立された神社であり、江戸時代(1754年)には義民として知られる佐倉惣五郎が佐倉藩主・堀田正信によって合祀されたそうです。
なお、石碑に記される詳しい由緒は以下の通りです。
将門神社(平親王将門大明神)
平小次郎将門(たいらのこじろうまさかど)は、平安時代に板東の地に桓武6代の帝系として生まれました。
一族の横暴と都での栄華を極める藤原摂政政治のもとに苦しむ民衆のために決起し、瞬く間に板東一円を治め、平親王と名乗りましたが、志半ばにして非業の最期を遂げたと言われています。
死後、多くの民衆から板東の英雄として追慕する声が高まり、各地に将門神社が建立されました。
大佐倉の将門神社の創建は定かではありませんが、桓武平氏の同族である本佐倉城主の千葉氏によって建立されたと伝えられています。石の大鳥居は承応3年(1654年)に佐倉藩主・堀田正信公(ほったまさのぶ)によって奉献されたと記録されています。
奥ノ宮の桔梗塚は将門の愛妻の桔梗の墓といわれていますが、将門を偲び、この地には桔梗の花は咲かないという言い伝えがあります。
口ノ宮神社(口ノ明神)
江戸時代、高い税に苦しむ百姓を救うため、将軍に直訴した佐倉惣五郎(さくらそうごろう)は、義民として映画や芝居になり広く知られています。
惣五郎百年忌(1754年)に際し、藩主・堀田正亮公(ほったまさすけ)によって口ノ明神に祀られ、宝珠院が別当として祭祀を行い、佐倉藩の保護の下に下総一円の領民に崇敬されてきたといわれています。
大正8年には本社、拝殿などを失火しましたが、地元大佐倉の氏子・世話人・有志により、惣五郎の命日といわれる9月3日には「宮なぎ行事」として毎年供養と祭祀が行われています。
平小次郎将門(たいらのこじろうまさかど)は、平安時代に板東の地に桓武6代の帝系として生まれました。
一族の横暴と都での栄華を極める藤原摂政政治のもとに苦しむ民衆のために決起し、瞬く間に板東一円を治め、平親王と名乗りましたが、志半ばにして非業の最期を遂げたと言われています。
死後、多くの民衆から板東の英雄として追慕する声が高まり、各地に将門神社が建立されました。
大佐倉の将門神社の創建は定かではありませんが、桓武平氏の同族である本佐倉城主の千葉氏によって建立されたと伝えられています。石の大鳥居は承応3年(1654年)に佐倉藩主・堀田正信公(ほったまさのぶ)によって奉献されたと記録されています。
奥ノ宮の桔梗塚は将門の愛妻の桔梗の墓といわれていますが、将門を偲び、この地には桔梗の花は咲かないという言い伝えがあります。
口ノ宮神社(口ノ明神)
江戸時代、高い税に苦しむ百姓を救うため、将軍に直訴した佐倉惣五郎(さくらそうごろう)は、義民として映画や芝居になり広く知られています。
惣五郎百年忌(1754年)に際し、藩主・堀田正亮公(ほったまさすけ)によって口ノ明神に祀られ、宝珠院が別当として祭祀を行い、佐倉藩の保護の下に下総一円の領民に崇敬されてきたといわれています。
大正8年には本社、拝殿などを失火しましたが、地元大佐倉の氏子・世話人・有志により、惣五郎の命日といわれる9月3日には「宮なぎ行事」として毎年供養と祭祀が行われています。
祭神
|
|
将門口ノ宮神社の祭神は以下の通りです。
主祭神
・平将門公(たいらのまさかど):平安時代に活躍した関東の豪族であり、民衆を救ったとして関東では英雄視される
→ 将門口ノ宮神社では「将門大明神」として祀られている
→ 死後も首だけで生き続けたとする伝承があり、日本最強の怨霊としても有名である
・佐倉惣五郎(さくらそうごろう):江戸時代に百姓を救うために藩主に直訴し、苛政を収めた義民として知られる
→ 将門口ノ宮神社では「口ノ明神」として祀られている
→ 藩主に直訴した後、妻と男児ともども死罪とされたため、藩主の堀田氏を祟ったとも云われている
・平将門公(たいらのまさかど):平安時代に活躍した関東の豪族であり、民衆を救ったとして関東では英雄視される
→ 将門口ノ宮神社では「将門大明神」として祀られている
→ 死後も首だけで生き続けたとする伝承があり、日本最強の怨霊としても有名である
・佐倉惣五郎(さくらそうごろう):江戸時代に百姓を救うために藩主に直訴し、苛政を収めた義民として知られる
→ 将門口ノ宮神社では「口ノ明神」として祀られている
→ 藩主に直訴した後、妻と男児ともども死罪とされたため、藩主の堀田氏を祟ったとも云われている
石鳥居
将門口ノ宮神社の石鳥居です。
佐倉藩主・堀田正信によって承応3年(1654年)に寄進されたものであり、佐倉市の指定文化財になっています。
マテバシイ
将門口ノ宮神社の馬刀葉椎(マテバシイ)です。
佐倉藩主・堀田正亮によって宝暦4年(1754年)に植えられたものとされ、佐倉市の指定文化財になっています。
社殿
将門口ノ宮神社の社殿です。
小さな社殿に垣が設けられ、鈴と狛犬が配されています。
祠
将門口ノ宮神社の社殿の裏には小さな祠があります。
料金: 無料
住所: 千葉県佐倉市大佐倉1929-1
営業: 終日開放
交通: 大佐倉駅(徒歩10分)
住所: 千葉県佐倉市大佐倉1929-1
営業: 終日開放
交通: 大佐倉駅(徒歩10分)
スポンサーリンク
|
|

「日本神話」を研究しながら日本全国を旅しています。旅先で発見した文化や歴史にまつわる情報をブログ記事まとめて紹介していきたいと思っています。少しでも読者の方々の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
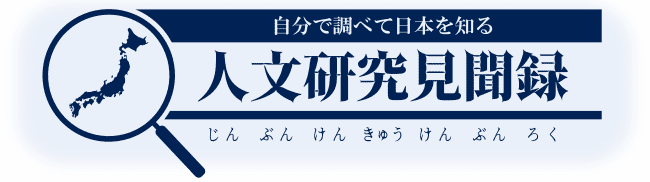
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisqXzO2FoZoJCDwjAV9sZwb_2soWsepYcKyO77o_6husvbUl3T47Yd6npgUywJkKQCB5dO8EzKJxBui2iGSOUARzEcGJqvYUKsHhzn3FYzEmxNGQcDhmF0x3qXS6JlG9py5TZtGtF3M6Sx/s400/fe3e6f1124fc45c181d6c3b9f0501434.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyTGS_qfN86hSC7so6bo3W9KsNgLbn7V-_NuGCMgeQV4pgSff-DnEC3YfhQK637CnzvsHzuz6Opmae3Ky3j-pehEoDcmu5JVnTdN1X9_UB8DST7VRoj-v0yeVGZOivgBNZOxeRxQaW_Bq/s200/8a76366d52a84d2c806cdfb3593b5257.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm7EKO7hw-TzAuLNG46AhGuCM3FURUhTjG_2eIK9-CBXRs5C-sgJUEYPmBQ5K1ehgfn43MIzQY8N5PQJAKM8i9AU8_3lPAinMnKJdg_8cMDE6DBpdNvGEc7NfBvYMlXB7_mla5gYEyVYf7/s200/04bcfe479abb40edb9bc10371a894412.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ltPwIB_aciusrfwf0XsHT7hMc1BI17nv3RS51ZvISF0MHaFUUiQD2r2bs7lg8DshCH8mVtugEPMkzCoFe_qvZDTuMVh0Nl1ZxIuOpNFY1TzbGBOiWrC7qWfqhOrF_01DUwZ8l_QmX_a3/s320/7e03781996604ceebebf59e02961c915.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy0VuqPuHsjxV5eoo_k-TcVs7upY48zqtCGZHZvnzjvU2rKy94sG2r2ArG3HI-jcwTbtCxwDOlgRyv7IFTY7H9GkBt7K-vMTiJGDFJfMCrlIT1bjmcBMvKawx3gepYBXlNON6ac8MPQ03P/s320/3d56f707930a4de1a53ff6485844d49c.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjAdbxu_oH4GS002SyTsc2junDbPbDWaeZZ8BushQRePXpirn9LvjE4xRkdLx6U2x8YScIl03JK23exIvqU__tQIJiQhAxZIoYphkYk5tbMWUuIPVMRsl5KLcRjpWq71Xit_WiNq0ReWkG/s320/6ba9f5a5377c4268865eac27a25a6bc7.jpg)
![人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県] 人文研究見聞録:将門口ノ宮神社 [千葉県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje8oj1Bc8AQY3IqAWVADi36Zb-9KqHgCh1kQJeBqWzuvsq1vHrCoDd68450wymCUg3uhXUCMkkbEGZyckHGyeyo7H1ykLGDmFscekhZ0BRna4R_Uv4hBhINhe-dSqzceEs6e0_JbwBS-wC/s320/7340aae40c0849dbadcd4280fffb5415.jpg)
コメント
1 件のコメント :
マテバシイは写真の木ではないと思いますよ?
コメントを投稿