狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]
2015/09/08
奈良県桜井市三輪にある狭井神社(さいじんじゃ)です。
花鎮社(けちんしゃ)とも通称される大神神社の摂社であり、大物主大神の荒魂神を祀っていることから、正式名称は「狭井坐大神荒魂神社(さいにいますおおかみ あらみたまじんじゃ)」とされています。
病気平癒の神社として知られており、境内には「くすり水」という御神水が湧きでています。また、御神体である三輪山への登拝口があり、山頂の「高宮社」に参拝するためには ここから登山する必要があります。
神社概要
概要
狭井神社は第11代垂仁天皇の時代(紀元前1世紀頃)の創祀と伝わる古社であり、本社・大神神社の祭神である大物主神の「荒魂(あらみたま)※」を祀っています(本社では大物主神の「和魂(にぎみたま)※」を祀っています)。
「荒魂」とは進取的で活動的な働きをする神霊を指し、災時などに顕著に働くとされています。特に身心に関係する篤い祈りに霊験あらたかな御神威を授け、多くの人々から病気平癒の神として崇められています。
現在、「くすり祭り」として知られる「鎮花祭(はなしずめのまつり)」は、平安初期(833年)に成立した『令義解(りょうのぎげ)』に「春花飛散する時に在りて、疫神分散して癘(えやみ)を行ふ。その鎮遏(ちんあつ)の為 必ず此の祭りあり。故に鎮花(はなしずめ)といふ也。」と記され、万民の無病息災を祈る重要な国家の祭として定められているそうです。
また、社名の「狭井」とは、神聖な「井戸・泉・水源」を意味しており、そこに湧き出る霊泉は太古より「くすり水」として信仰の対象になっているとされています。
※荒魂(あらみたま):神の荒々しい荒ぶる側面である。天変地異を引き起こし、病を流行らせ、人の心を荒廃させて争いへ駆り立てる神の働きである。
※和魂(にぎみたま):神の優しく平和的な側面である。雨や日光の恵みなどの神の加護は和魂の表れであるとされる。
祭神
狭井神社の祭神は以下の通りです。
主祭神
・大神荒魂神(おおみわのあらみたまのかみ):大物主の荒魂
配祀神
・大物主神(オオモノヌシ):大神神社の主祭神と同神であり、一般的にはオオナムチの別名とされている
→ 『ホツマツタヱ』によれば、"軍事を司る役職名"もしくは"ミモロヤマ(三輪山)に鎮まる神"を指す
⇒ 正式名称から、第5代大物主に当たるクシミカタマの名を以ってオホナムチのサキミタマを祀ったものを考えられる
・姫蹈鞴五十鈴姫命(ヒメタタライスズヒメ):初代 神武天皇の妃
・勢夜陀多良姫命(セヤタタラヒメ):姫蹈鞴五十鈴姫命の母
・事代主神(コトシロヌシ):一般的にはオオナムチの子神とされる
→ 『ホツマツタヱ』によれば、タタライソスズヒメの父のツミハ(積羽八重事代主神)に当たると思われる
・大神荒魂神(おおみわのあらみたまのかみ):大物主の荒魂
配祀神
・大物主神(オオモノヌシ):大神神社の主祭神と同神であり、一般的にはオオナムチの別名とされている
→ 『ホツマツタヱ』によれば、"軍事を司る役職名"もしくは"ミモロヤマ(三輪山)に鎮まる神"を指す
⇒ 正式名称から、第5代大物主に当たるクシミカタマの名を以ってオホナムチのサキミタマを祀ったものを考えられる
・姫蹈鞴五十鈴姫命(ヒメタタライスズヒメ):初代 神武天皇の妃
・勢夜陀多良姫命(セヤタタラヒメ):姫蹈鞴五十鈴姫命の母
・事代主神(コトシロヌシ):一般的にはオオナムチの子神とされる
→ 『ホツマツタヱ』によれば、タタライソスズヒメの父のツミハ(積羽八重事代主神)に当たると思われる
三輪山登拝口
狭井神社には三輪山への登拝口があり、受付も狭井神社で行われています。
この登山口の先にある三輪山の山頂には摂社・高宮神社や奥津磐座があります。
なお、登山条件および境内社の祭神は以下の通りです。
登拝条件
・登拝料:300円(団体申込不可)
・受付時間:9:00~14:00(時間厳守)
・下山報告:16:00(時間厳守)
・禁止事項:飲食(水分補給以外)・火器の使用・カメラなどでの撮影 ほか
・入山登拝禁止日:1月1日~3日、2月17日、4月9日・4月18日(午前のみ)、10月24日、11月23日(天候にもよる)
・登拝料:300円(団体申込不可)
・受付時間:9:00~14:00(時間厳守)
・下山報告:16:00(時間厳守)
・禁止事項:飲食(水分補給以外)・火器の使用・カメラなどでの撮影 ほか
・入山登拝禁止日:1月1日~3日、2月17日、4月9日・4月18日(午前のみ)、10月24日、11月23日(天候にもよる)
摂社・高宮神社(こうのみやじんじゃ)
【概要】
・上宮、神峰社とも称される
・大神神社社蔵の古絵図には「神上ノ宮」と表記されている
・室町時代の「三輪山絵図」には「神坐日向神社」と表記されている
・江戸時代の地誌『大和名所図会』には、神坐日向神社は「三輪山の嶺にあり、今、高宮と称す」とある
・三輪山は御留山とも呼ばれ、古くから禁足地とされてきたと云われる
・江戸時代には、特別の時に限り高宮神社の登拝を許されたとされる
・社家・神主は厳重な参籠および斎戒沐浴の上で高宮神社に登拝し、祈雨祭を奉仕している慣例があるという
【祭神】
・日向御子神(ひむかいみこかみ):詳細は不明だが、『記紀』における「海を光して依り来る神」に当たると推測される
→ 別名・日向王子
→ 『ホツマツタヱ』においては、オホナムチとクシミカタマのサキミタマ(クシヰワザタマ)と推測される
⇒ サキミタマは"肉体に宿っていない部分の上位神霊"と解される
→ "大物主神の御子"とも云われる
⇒ 『ホツマツタヱ』では、大物主は"軍事を司る役職名"もしくは"ミモロヤマ(三輪山)に鎮まる神"を指す
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「オホナムチの子のクシヒコが天逆矛を持って三諸山の洞に籠った」という記述がある
【概要】
・上宮、神峰社とも称される
・大神神社社蔵の古絵図には「神上ノ宮」と表記されている
・室町時代の「三輪山絵図」には「神坐日向神社」と表記されている
・江戸時代の地誌『大和名所図会』には、神坐日向神社は「三輪山の嶺にあり、今、高宮と称す」とある
・三輪山は御留山とも呼ばれ、古くから禁足地とされてきたと云われる
・江戸時代には、特別の時に限り高宮神社の登拝を許されたとされる
・社家・神主は厳重な参籠および斎戒沐浴の上で高宮神社に登拝し、祈雨祭を奉仕している慣例があるという
【祭神】
・日向御子神(ひむかいみこかみ):詳細は不明だが、『記紀』における「海を光して依り来る神」に当たると推測される
→ 別名・日向王子
→ 『ホツマツタヱ』においては、オホナムチとクシミカタマのサキミタマ(クシヰワザタマ)と推測される
⇒ サキミタマは"肉体に宿っていない部分の上位神霊"と解される
→ "大物主神の御子"とも云われる
⇒ 『ホツマツタヱ』では、大物主は"軍事を司る役職名"もしくは"ミモロヤマ(三輪山)に鎮まる神"を指す
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「オホナムチの子のクシヒコが天逆矛を持って三諸山の洞に籠った」という記述がある
奥津磐座(おきついわくら)
【概要】
・三輪山の山頂(標高467.1m)にある磐座で、当山における聖域とされる
【祭神】
主祭神
・大物主大神(オオモノヌシ):一般的には大神神社の主祭神と同神とされる
→ 第2代大物主の奇彦命(クシヒコ)という説がある
⇒ 奇彦命は大己貴命(奇杵命)の子神であり、『記紀』における事代主神に当たる
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「クシヒコは2代目大物主であり、晩年に三諸山の洞に籠った」という記述がある
配祀神
・大己貴神(オオナムチ):一般的には出雲大社の主祭神である大国主大神と同神とされる
→ 第5代大物主の蕗根命(フキネ)という説がある
⇒ 『ホツマツタヱ』では4代大物主に当たり、「トヨツミヒコと共に筑紫32県を治めた」とされる
・少彦名神(スクナヒコナ):オオナムチと共に国造りを成した神とされる
→ 豊祇彦命(トヨツミヒコ)という説がある
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「トヨツミヒコは大物主・フキネと共に筑紫32県を治めた」という記述がある
【概要】
・三輪山の山頂(標高467.1m)にある磐座で、当山における聖域とされる
【祭神】
主祭神
・大物主大神(オオモノヌシ):一般的には大神神社の主祭神と同神とされる
→ 第2代大物主の奇彦命(クシヒコ)という説がある
⇒ 奇彦命は大己貴命(奇杵命)の子神であり、『記紀』における事代主神に当たる
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「クシヒコは2代目大物主であり、晩年に三諸山の洞に籠った」という記述がある
配祀神
・大己貴神(オオナムチ):一般的には出雲大社の主祭神である大国主大神と同神とされる
→ 第5代大物主の蕗根命(フキネ)という説がある
⇒ 『ホツマツタヱ』では4代大物主に当たり、「トヨツミヒコと共に筑紫32県を治めた」とされる
・少彦名神(スクナヒコナ):オオナムチと共に国造りを成した神とされる
→ 豊祇彦命(トヨツミヒコ)という説がある
⇒ 『ホツマツタヱ』には、「トヨツミヒコは大物主・フキネと共に筑紫32県を治めた」という記述がある
参考サイト:大神神社の摂社・末社、三輪山の高宮神社
境内の見どころ
鳥居
狭井神社の鳥居です。
縄鳥居
狭井神社の縄鳥居(なわとりい)です。
柱に注連縄の掛けられた古いタイプの鳥居であり、二の鳥居として拝殿前に設けられています。
拝殿
狭井神社の拝殿です。
本社の大神神社と同様に本殿は無く、背後にそびえる神体山である三輪山を拝めるような形となっています。
御神水「くすり水」
|
|
狭井神社の御神水である「くすり水」です。
この御神水は神体山・三輪山から湧き出た湧水であり、古くから霊験あらたかな霊水として、飲めば 病気平癒・身体健康・福寿延命などの御利益があるとされています。
水の湧き出る磐座に蛇口が取り付けられ、蛇口のボタンを押すことで水が汲めるようになっており、ペットボトルなどに注いで飲むような仕様となっています。
なお、付近には参拝者用のコップも用意されています(滅菌使用)。
持ち帰ることは可能ですが、山の湧き水であるため日に湧く量に限りがあり、むやみやたらに垂れ流したり、大量に持ち帰ることは禁じられています。マナーを守って霊水を頂きましょう。
スポンサーリンク
|
|

「日本神話」を研究しながら日本全国を旅しています。旅先で発見した文化や歴史にまつわる情報をブログ記事まとめて紹介していきたいと思っています。少しでも読者の方々の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
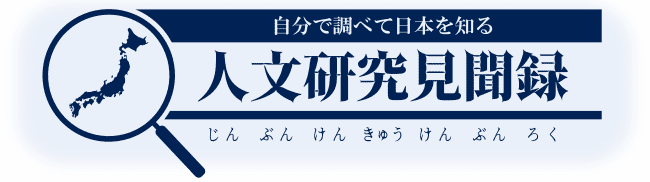
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4YQ4hA9pa7475UrWM85SaWT6zKxRz5NF7epgv7SUwM5IUGW-lpyLcFG_MrTdBSqYY4yom63TFZIjXpesxvVIF1RyacREkoaPeCXNJFNYlg3ecx0zaXahXgiVpcTCoZrsFlanxRExaEgAM/s400/cca0ced1-cec5-4061-b39c-90ae3144210f.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFshnbkzwH5T_mzYqwJuoI28TtjEGvMX7Kfqrbd0nRik9ID7-VxnoHjXH4JiBDviuOP3RpLsBL76cpKl1NsYN1Fxpx96EkdG-grbRZLuO-UhIA31nZdYPw55hgOs8zJPGThkiXafpZFiw/s320/89047700344c4a138b3ad51555a1a01d.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG86lGIcGTMy5Fq7Ln_VTZbLpDDgdJWMVUfF_jE-YLWlUhEGGecxKUZNPkcSg_LQ6zZJ6XpsctpmeHBlNIhIBLSSU7djZVqssiTrov8yb1WUlvarIX4BmuOMQsz48dlsokkSOwBe3p8SY/s320/6a03089fb9244d9bbcb566b379566bf7.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBpwYH7VrMxKIrBo5GOk_TbwSsk9OCUpRGLaSHF6kA2f4MUc2lKsuVORpbvcB1gP7C4TavPBv0qaR1A2QH25iBj9FlUJZG5Oe1M9i_G26LlgzoV2L1CTLuK7fLWrCtg3tZPDmXj-n2k3U/s320/9fe977995f3143c291267034113ef126.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPTqSeLAzqynfp0_O3EMoPIjBYtgqwDYhEeKkHGq9iphWz3xDuqbYsf4QcUzCFIHx8T0QRNex9UPwNC_83ELhT1WgW6MU-VgCUwjhVaJE1Bp3bkYEB4e0JCvrXI72HzEYiv_mH7j8Org/s320/a5c96687d2784826b206ddad8a4bb40b.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-usCXhBREM6ZTjw0elugm97rb-osWfv2jZTmlh7BObevEjPoVfftbNiQCEWH4iyyQJIBwYttkN5UvanAbtZEwWPI7Nps3LxlOjPy_RCIOFG7Y9bSmyYdXnooHj_TVvbwJOdro-lDO4wQ/s320/3dfdf5ced7264a8baa3b6fd1ff8430ee.jpg)
![人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県] 人文研究見聞録:狭井神社(狭井坐大神荒魂神社) [奈良県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrWJW30JskAGIwM9wHyQtnkEAbEpPblE9mX4s4b9KRFBjMy-bzjrES5Ug2sXCmgPUHIuo5qLhzURGthwD10FLTKJZHY2nUN8JL_WVvJYLeGlWBn-DdS_WIMiyjnO2ZHvNVSnb7MmE9oHY/s320/b4912553f59a4483a9b80d8973a017aa.jpg)
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿