猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]
2016/06/29
新潟県柏崎市にある猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)です。柳橋道祖神(やなぎばしどうそしん)とも呼ばれています。
柏崎駅の沿線にある小ぢんまりとした神社であり、猿田彦命と習合した土着の道祖神を祀っているとされています。
神社概要
由緒
由緒書によれば、当社は「柳橋道祖神」と呼ばれる道祖神を祀っており、当初は鵜川神社(柏崎市宮場町)に祀られていたとされています。
その後、南北朝時代の延文年間(1356~1360年)に泉州信太郡(現・大阪府和泉市)の関四郎五郎という信仰の篤い人が琵琶島に移住し、道祖神の社を造営して以来、現地に祀られることになったそうです。
なお、道祖神や由緒についての詳しい記述は以下の通りです。
道祖神の由来(由緒書転載)
道祖神(どうそしん)は「塞の神(さいのかみ)さま」と呼ばれ、本来は悪霊をさえぎって村に侵入するのを防いだ神様であった。多くは村境、峠、辻などに祀られていた。
道祖神が猿田彦命(サルタヒコ)だといわれるのは、天津神降臨の道案内をしたという神話に基づいている。
道祖神の形は色々あって、石に道祖神を彫ったもの、男女二神が手を取り合って和合の姿を示した双体道祖神、男根・女陰を模った物など、石造物として面白いものが多い。
「柳橋道祖神さま」は、大きな古い石で単体の道祖神様である。
道祖神は「庚申(こうしん)さま」や「お地蔵さま」が習合していくうちに様々な性格を持つようになった。「旅の安全を守る神」「縁結びと縁切りの神」「子供の守護神」「子授け子育ての神」「性の神」「豊作の神」などで村の守り神として広く親しまれていた。
ところで、「柳橋の道祖神さま」は鵜川神社に祀られてあったのだが、いつの時代からか柳橋に移ったのである。
延文年間(1356~1360年)泉州信太郡の人で関四郎五郎という信仰の篤い御方が琵琶島に居住し、道祖神の社を造営されたのであると歴史は伝えている。云々
※多少加筆修正しています。
道祖神(どうそしん)は「塞の神(さいのかみ)さま」と呼ばれ、本来は悪霊をさえぎって村に侵入するのを防いだ神様であった。多くは村境、峠、辻などに祀られていた。
道祖神が猿田彦命(サルタヒコ)だといわれるのは、天津神降臨の道案内をしたという神話に基づいている。
道祖神の形は色々あって、石に道祖神を彫ったもの、男女二神が手を取り合って和合の姿を示した双体道祖神、男根・女陰を模った物など、石造物として面白いものが多い。
「柳橋道祖神さま」は、大きな古い石で単体の道祖神様である。
道祖神は「庚申(こうしん)さま」や「お地蔵さま」が習合していくうちに様々な性格を持つようになった。「旅の安全を守る神」「縁結びと縁切りの神」「子供の守護神」「子授け子育ての神」「性の神」「豊作の神」などで村の守り神として広く親しまれていた。
ところで、「柳橋の道祖神さま」は鵜川神社に祀られてあったのだが、いつの時代からか柳橋に移ったのである。
延文年間(1356~1360年)泉州信太郡の人で関四郎五郎という信仰の篤い御方が琵琶島に居住し、道祖神の社を造営されたのであると歴史は伝えている。云々
※多少加筆修正しています。
祭神
猿田彦神社(柳橋の道祖神) の祭神は以下の通りです。
主祭神
・柳橋の道祖神:当社の道祖神は「塞の神」として祀られていた神で、多くの神仏と習合して現在に至るとされる
→ 日本神話の天孫降臨に基づいて猿田彦命(サルタヒコ)とも習合しているとされる
・柳橋の道祖神:当社の道祖神は「塞の神」として祀られていた神で、多くの神仏と習合して現在に至るとされる
→ 日本神話の天孫降臨に基づいて猿田彦命(サルタヒコ)とも習合しているとされる
境内の仏塔・石碑について
境内には本殿の他に石祠をはじめ、「二十三夜塔」や「庚申塔」などの石碑が祀られています。
これらについて本殿内に説明書があったので、ここに転載しておきます。
二十三夜塔(にじゅうさんやとう)について
18世紀の後半から昭和初期にかけて、日本各地で「講(こう)」を組織した人々が集まって月を信仰対象として精進・勤行を為し、飲食を共にしながら月の出を待つ「月待ち」の行事をしました。
その際、供養の印として建てた石碑である月待塔(つきじとう)の一つが二十三夜塔(にじゅうさんやとう)です。
崇拝の対象として十三夜は虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)、十五夜は大日如来(だいにちにょらい)、十七夜から二十二夜までは観音様を本尊とし、二十三夜は勢至菩薩(せいしぼさつ)を本尊として祀りました。
勢至菩薩は知恵の光を持っており、あらゆるものを照らし、全ての苦しみを離れ、衆生に限り無い力を得させる菩薩と云われています。月は勢至菩薩の化身であると信じられていたことから、二十三夜講が最も一般的で全国に広がりました。
※多少加筆修正しています。
18世紀の後半から昭和初期にかけて、日本各地で「講(こう)」を組織した人々が集まって月を信仰対象として精進・勤行を為し、飲食を共にしながら月の出を待つ「月待ち」の行事をしました。
その際、供養の印として建てた石碑である月待塔(つきじとう)の一つが二十三夜塔(にじゅうさんやとう)です。
崇拝の対象として十三夜は虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)、十五夜は大日如来(だいにちにょらい)、十七夜から二十二夜までは観音様を本尊とし、二十三夜は勢至菩薩(せいしぼさつ)を本尊として祀りました。
勢至菩薩は知恵の光を持っており、あらゆるものを照らし、全ての苦しみを離れ、衆生に限り無い力を得させる菩薩と云われています。月は勢至菩薩の化身であると信じられていたことから、二十三夜講が最も一般的で全国に広がりました。
※多少加筆修正しています。
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikGxDMXMDOYk5-RhzA9tuaQyFpeCM3mKGO-m9uhunYQIaBAohv6NXbWOr0U2dhuqDfSw6VZwpid4X-1i1TwQf2g4KdiVwvTPWyYkY-aSsLBpdrV5NN5yHpiNg_mW5tp-rs7JJSUJJ_QFWH/s320/db348b07-b92b-4ae8-b2dc-b40eacbd3530.jpg) |
| 三尸(さんし) |
庚申塔(こうしんとう)について
高い峠では あまり見ることはありませんが、峠沿いの村落の外れなどで見かけるのが この「庚申塔(こうしんとう)」です。
庚申塔のことを知るには「庚申信仰」のことを知る必要があります。
庚申信仰は、古くは中国の晋の時代、道教の思想から端を発し、奈良時代に日本に伝わった後、日本国有の信仰と結びついて発展してきました。
人の身体の中には「三尸(さんし)」という虫がいて、60日ごとに巡ってくる庚申(かのえさる)の日に人々が寝静まった夜、その虫が体内から出てきて天帝に その人の悪行を報告し、ここで天帝を怒らせれば その人を早死にさせてしまうと云われています。
そのため、庚申の日には寝ずに夜通し起き、三尸が体内から抜け出さないようにすることを「庚申待(こうしんまつ)」と言います。また、この時に一緒に庚申待を過ごす人の集まりを「庚申講(こうしんこう)」と言います。
当初は恐らく庚申待の夜は厳かに過ごすのが習いだったと思われますが、平安時代より「2ヵ月に一度の楽しい夜通しの宴会の日」となってしまい、娯楽に乏しかった時代に一気に全国の村々に広がって行きました。
そして、この信仰は60年に一度の庚申の年に庚申塔を建立することを原則としました。我が柳橋の道祖神境内にある庚申塔も、大正9年の庚申の年に建立されたものであると記されています。
なお、庚申は、風邪・咳などの治病神、あるいは作神、福神とみなされています。
※多少加筆修正しています。
境内の様子
鳥居と境内
猿田彦神社の様子です。入口には狛犬と石鳥居があり、石鳥居をくぐった先には道祖神、石碑類、本殿があります。
なお、この猿田彦神社は伊勢からの分祀などでは無く、土着の道祖神を祀っているようです。
道祖神
この祠に祀られている石像が道祖神であると思われます。
格子から覗いてみれば、由緒書にある通りに単体の道祖神となっています(地蔵っぽい)。
本殿内
猿田彦神社の本殿の内部です。
部屋の中央には神鏡と随神が祀られています。
なお、ここに由緒書やその他の説明書があります。
スポンサーリンク
|
|

「日本神話」を研究しながら日本全国を旅しています。旅先で発見した文化や歴史にまつわる情報をブログ記事まとめて紹介していきたいと思っています。少しでも読者の方々の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
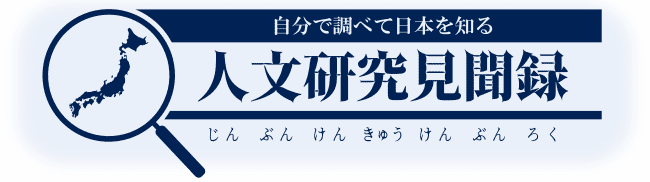
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL3RKOnGDvlTrXPKqETpQ4z-ybkRc0usnfJ4gKe7e8cWyY_FI9iJOez6AXm6xZOO5-kqyHj83X_lYhClfnMVpDxVDr_fO3VM6lbTwaSkICh7t8U3v7PR2DwXjlyg-kruWeS5FcTczsW9RD/s400/7b6b73d5-e362-4a06-bc7b-1ee3fe9b9d01.jpg)
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZrDLNsMSqim2jWs141gpoPxufka3LldgeEMwfXcJ2WcpjsrEQN5yKgh288PwNNP8unVz8Z-SujO1FklkClHeXRrJg8_pD8KpeS7kLsTGZTRB72EEviZNg7gMMdmuStbNzK9orLNhcd1S6/s320/147ab667-3dee-4757-8867-ba3d374f0a18.jpg)
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghzsfY0iWXmKLwuQZgKiwt2FRm5ez5HJbgHvbZ9-ewYar5rcHGkpI77an5nv1z8nDI-UbpFAdy7Vq4L4N2XJ92-TTVhL4rH39nAzydp6IS4wao0vUoqoAeMkoEkgTL6u63uHf44KDHTHyb/s320/bc6c00fa-b7a5-4231-a525-141802a83c60.jpg)
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdx_EbOM_pYpKtTQExMSkGfUMB8o77ychEZ_UPDwc6swvuDvnMWZQnBBPlougo6HuaC7cZudraVJnYeGrltGZFwhJjys8l6PzFMhQIzMX-HLy7H5-nFju9r-GynGsIHbBP9LdUevOGemuU/s320/f4fa0557-229e-46ab-a8e5-621ba7a833c4.jpg)
![人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県] 人文研究見聞録:猿田彦神社(柳橋の道祖神) [新潟県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHep_meRR20KrlkdHtwkiL_b7QKibTffMNwyLQkEf4urGMDKxm6A1j0Dn7uq3SrPa-N2Qki_KMg-SdpoGFEIXAVyBDs_mSk-KCXAnw0lEuDJMnoJi1WIm9GFasSy8LRl4acMq2ktiGtY2v/s320/c7883e41-b46c-4587-875a-a2e80b4d4c67.jpg)
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿