風土神社 [島根県]
2019/03/03
島根県出雲市佐田町にある風土神社(ふうとじんじゃ)です。
かつて須佐神社の末社であった古社で、祭神に志那都比古神・志那都比賣神を祀っています。
神社概要
由緒
由緒書によれば、当社は古くは須佐神社の末社(摂社)であり須佐国造所祭の社とされていましたが、明治17年(1884年)に独立し、原田地区の氏神として崇敬されて現在に至っているとされます。
なお、詳しい創建時期は不明とされるものの、天和2年(1682年)以降の棟札が現存していることや古老伝説(下記参照)などから室町時代に創建されたものと考えられているそうです。
また、当社の祭神は風の神であり、社号については「風戸大明神社」「風水大明神社」「風水神社」「風戸神社」などを経て、現在の社号である「風土神社」となったとされています。
祭神
風土神社の祭神は以下の通りです。
・志那都比古神(シナツヒコ):「日本神話」で神産みによって生まれた風の神(男女一対の男神に当たる)
・志那都比賣神(シナツヒメ):「日本神話」で神産みによって生まれた風の神(男女一対の女神に当たる)
・志那都比賣神(シナツヒメ):「日本神話」で神産みによって生まれた風の神(男女一対の女神に当たる)
関連知識
古老伝説
当社には風土神社の神が武将を助けたという以下のような伝説が伝えられています。
永禄年間(1558~1570年)に原田矢嶺山の城主で勝部筑前守という剛将がおりました。ある日、朝食をとっていたところ、突然一本の矢が飛来してきて食卓の前に落ちました。筑前守は大いに驚いて急いで鎧兜を身に着けて出てみれば、あたかも敵が襲わんとするところであり、直ぐに手兵を率いて奮闘力戦し、ついにこれを撃退しました。
そこで筑前守は、不思議に思って彼の食卓の上に落ちた矢が来たところを探してみたら、奇妙なことに風土神社の方から来たことがわかりました。ここにおいて筑前守は御神恩に大きく感激して、当社に感謝したということです。本殿にはその矢と勝部筑前守が寄進したとされる槍二本が社宝として献上されています。
そこで筑前守は、不思議に思って彼の食卓の上に落ちた矢が来たところを探してみたら、奇妙なことに風土神社の方から来たことがわかりました。ここにおいて筑前守は御神恩に大きく感激して、当社に感謝したということです。本殿にはその矢と勝部筑前守が寄進したとされる槍二本が社宝として献上されています。
境内の見どころ
鳥居
風土神社の鳥居です。
拝殿
風土神社の拝殿です。
本殿
風土神社の本殿です。
社日(地の神)
風土神社の社日です。
社日は当地でよく祀られている五角形の石塔で、田の神を祀っているといわれています。
なお、この五角形の各面には天照大神・大己貴命・少彦名命・埴山姫命・倉稲魂命と刻まれています。
スポンサーリンク

「日本神話」を研究しながら日本全国を旅しています。旅先で発見した文化や歴史にまつわる情報をブログ記事まとめて紹介していきたいと思っています。少しでも読者の方々の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
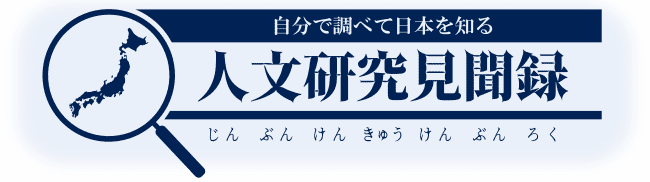
![人文研究見聞録:風土神社 [島根県] 人文研究見聞録:風土神社 [島根県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBYOinZkGV-QyDh_LfTOuZ5DRbE89n19vBwLlfvO7xbc5bAU4N8GMDr68ns_4fudOCgIU8jWUTr1FTvT3Fa-FGOJ7zjwXbuDN-JwZIgQWL9IlM0OLu9NShkXzKgf89YtERjdHXELHDsGZb/s400/iPHzK-min.JPG)
![人文研究見聞録:風土神社 [島根県] 人文研究見聞録:風土神社 [島根県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGUCZLIZp2LPRecblK21iLlXsW-JV1qmPt5imozrKA8VQxuXNSROcKEp5rhbdbqxCnxuylRbTqvYGwfIwAYT5FKTiWlyPwCo7WND-gjU4Ci4s_Pwy1QtGqp7P_3AZQ25UDBLvOABiGkyks/s320/cRWsR-min.JPG)
![人文研究見聞録:風土神社 [島根県] 人文研究見聞録:風土神社 [島根県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijS2DSBrtXsqphs_Jj9fpT3L7U5OfVDMFDohmfFuuTfF8-svB2hbBxlrRUnHNo_KZ_46MzfdY34QorMTqI_lWkM8q3T-6vpmqrag2Ke_kPYggA5i9oL4dsaHwLDYV7YM4kO2vVajqS5gv4/s320/6p2Zz-min.JPG)
![人文研究見聞録:風土神社 [島根県] 人文研究見聞録:風土神社 [島根県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0AHbJN2NcxeJR9MSHuz7F19l0yCZFtYyIrh6r7EdiAhl6rhMsjzR9nvQhelTNaw8x_qKxH_wtDbj4mgYqH52q8zrGkHfkVzgo_lB6NEbrb_rBTldrdRtcNoOC76qhNw4Njp9Hi9SjjBxv/s320/ctBNL-min.JPG)
![人文研究見聞録:風土神社 [島根県] 人文研究見聞録:風土神社 [島根県]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXWteeFAXiw5jfgTgfKDm-oJX3Ed79-jJfvauQQe08KBH09e7LAlIvlbGLW4tG9g5ggq4IkBnYItyYFYAnYLVQZ8Ec61gEwbrb-WYHJfUNB8qGA2iPulbZ9iyZ0Wd-q5mvjK3srF2TkGWv/s320/mu6mu-min.JPG)
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿